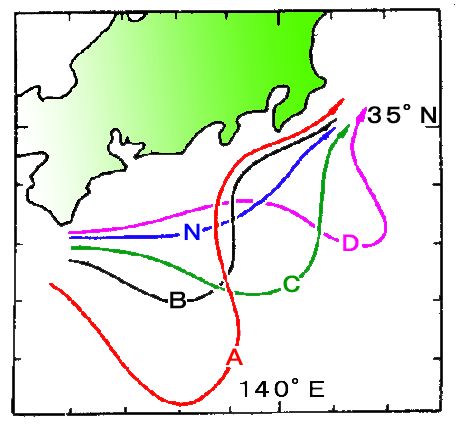�C���A���������̏��F��s�O���T�o���C�������
 �@�ҍ����u�ӂ��イ�v�@
�@�ҍ����u�ӂ��イ�v�@ �@�C���A���������̏��F��s�O���T�o���C���������@
�@�C���A���������̏��F��s�O���T�o���C���������@ �@�ߘa6�N1���`6���̌������C���\��
�@�ߘa6�N1���`6���̌������C���\��
|
�ߘa6�N�����T�o�����������ԋ��A�_��ԋ��̌����݁i�ߘa5�N1�`6���j
�ߘa7�N02��07���F�É������Y�E�C�m�Z�p������
�P�D�C��
�i1�j�����i2025�N1�`6���j
�i2�j����
�P��8�����݁A�����͉��B�剫���r����ɖk�サ����ɓ��i���A�K�F�C���O����ӂ�ʉߌ�A�k���Ɍ�����ς��[�����𗬂�Ă���B�����́A�ɓ������k���C���20�`21���A�O����Ӌy�ёK�F�C���21���ɂȂ��Ă���B
�����͊��Ԃ�ʂ���A�^�Ő��ڂ���B�֍s�œ쉺������x�͘p�`�ΘL�鉫��k�サ����A�K�F�t�߂Ō����𓌁`�k���ɕς��A�ɓ������k����O��t�߂�ʉ߂���B���̂��߁A�����̊C��ł͗�N�������ꐅ�����㏸���A20���ȉ��ɂȂ�ɂ����B�[�����ł͊T�ːڊX���Ő��ڂ��A���݂͈ꎞ�I�ł���B�܂��A��������̒g���ɕ����₷���B
|
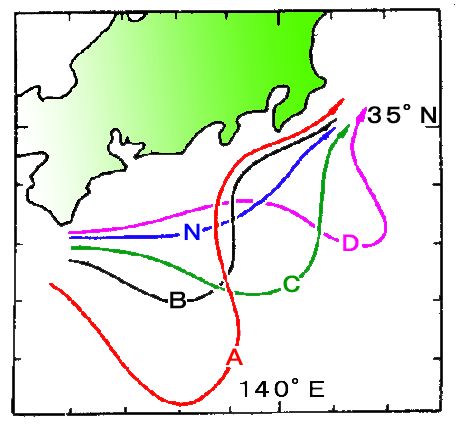 |
����ʃg�b�v�ɂ��ǂ�
�Q�D�}�T�o�̋���
�i1�j�\���i2025�N1�`6���j
�@�i�A�j���V�ʂƋ��l��
�i2�j����
�i�A�j���V�ʂƋ��l��
2025�N�P�`�U���̈ɓ������C��ɂ�����}�T�o���V�ʋy�ы��l�ʂ́A2024�N������錩���݂ł���B����́A���Y�����E����@�\�����\����}�T�o�����m�n�Q�̎����ʗ\���y�ыߔN�̊C�m���܂��ē����o�������ʂł���B
�܂��A���@�\�ɂ��A���n�Q�̎����ʁi�b��l�j��2018�N���s�[�N�Ɍ����X���������Ă���B�ɓ������C��ɗ��V����̂͐��n�����e�������S�ƂȂ邪�A��z�I�ȉ�����������2013�N���Q�ȍ~�͐����x���i�R���u�ߘa�R(2021) �N�x�}�T�o�����m�n�Q�̎����]���v�j���F�߂��邱�Ƃ���A���n�����R����30���y�тS�Έȏ��100%�Ɖ��肵�Đe���ʂ𐄒肵�A2025�N�P�����_�̐e���ʂ�235��g���Ɨ\�������B����͒ᒲ�ł������O�N���ł���B
���ɁA�C�m���ɂ��ẮA�����������k�E���݊��ɗ�����Ԃ�2022�N�ȍ~�p�����Ă���A2025�N�P�����{�����̏������Ɨ\������Ă���i2024�N��S�k�C��C���\��j�B�����āA2024�N12�����_�̓��k�C��ɂ�����ܓx�o�x�T�����ƂŏW�v�������ꐅ���̕��ς�20.2���i�O�N�F18.4���A2019�`2023�N���ρF16.1���j�ƑO�N�����鍂���ł���B���̂��Ƃ���A�C�m���͑O�N�ȏ�Ɉ������Ă���A�e���̓쉺�͑O�N��������ł���Ɣ��f����邱�Ƃ���A���V�ʂ͑O�N�������ƍl������B
���̂悤�ȏ��A2022�N�ȍ~�̍��������̖k�ɂ���Đe���ʂɑ��鋙�l�����i���l��/�e���ʁj�͋ɂ߂ĒႢ��Ԃ������Ă���A���l�w�͗ʂ��قƂ�Ǖς���Ă��Ȃ����Ƃ��l������ƁA���̒Ⴂ���l�����͊C�m���̕ω��ɔ������V�ʂ̌����f�������ʂł���B����2024�N�͍Œ�l���L�^�����B2025�N�̋��l���������ɉߋ��T���N�i2020�`2024�N�j�̕��ςŎ��Z����ƁA���l�ʂ�876�g���ƂȂ�A2024�N�����錩���݂ł���B����ŁA�ߋ��Œ�l���L�^����2024�N�̋��l�����Ŏ��Z�����ꍇ�A���l�ʂ�356�g���ƂȂ�A2024�N���̐����ɂȂ�B�������A�����̎��Z�͊y�ϓI�ȗ\���ɉ߂����A���ۂɂ͗��V�ʂ��O�N�������ƍl������ƂƂ��ɁA���l�w�͗ʂ��O�N���l�ł��邽�߁A���l�ʂ͑O�N�������Ɨ\������B
���\���P�F2025�N�̋��l�������ߋ��T���N���ςƂ����ꍇ�̎��Z�l
�i�C�j�����E����
2025�N�̈ɓ������C��ɂ�����}�T�o�������i�����ŏ��߂Ă܂Ƃ܂������l��������j�́A�Q�����{�ȍ~�ƂȂ�ߔN�ōł��x���Ȃ�\��������B�Ȃ��A����͖k���C��i�哇��g�E�������Ӂj�Ɍ`������錩���݂ł���B����́A2024�N12�����_�ɂ�����e�n�̃}�T�o���g���A���k�C��̈ܓx�o�x�T�����ƂŏW�v�������ꐅ���̕��ρAFRA-ROMS�U�Ŏ����ꂽ�C�������Ƃɐ��肵�����ʂł���B
2016�`2022�N�̏������͂P�����{�`�Q����{�ł��������A�����������k�����k�C��̐������㏸����2023�N��2024�N�͓쉺���x��A��������Q�����{�������ƂȂ����i�\�Q�j�B2025�N�́A12�����_�̓��k�C��̐������O�N�����鍂���ł��邱�Ƃɉ����A�P�����{�܂ō��������̖k���p�����錩�ʂ��ł��邱�Ƃ���A��V�̒x�ꂪ��w�����ɂȂ�Ɛ��肳���B
�}�T�o�̓쉺�ɂ��Ă͂Q�̃O���[�v�ɕ����čl�����B�P�ڂ́A��֖k���ŋ��l�@�@����Ă��������27�`30cm��̂̋��Q�ł���B���̂��������R���̈ꕔ�����n�ɔ����@�쉺����ƍl������B��֖k����2024�N12�����_�Ŏ務��ł���A���q���`�ł͌���3,000�g�����x�����g������Ă��邪�A2023�N�̓������͌��i�鉫���務��ł��������Ƃ���A2024�N�͓쉺���x��Ă��邱�Ƃ��f����B�Q�ڂ́A�{�錧�����u�Ԃ�12��23����35�g���̐��g�����m�F���ꂽ�쉺�Q�Ǝv���鐬���̋��Q�i������31�`35cm��́j�ł���B�����̐��g���͗�N�����x���A�쉺�̒x�ꂪ���炩�ł���B
�܂��A��N12������P���Ƀ}�T�o�����g��������t���O�[�C��i��u�ԁE�n�C�J���@�ނ�E�����D�j�ł́A�P���X�����_�ł��쉺�Q�ƍl�����鋛�̂��m�F����Ă��Ȃ��B���̂��Ƃ��A�쉺����N���x��Ă��邱�Ƃ������Ă���B
�Ȃ��A�}�T�o�̈ɓ������C��ւ̗��V�́A��^�̋��Q����s���A���^�̋��Q���x��ė��V���邱�Ƃ��m���Ă���B�������A12�����_�̕��z������ƁA���^�̋��Q�i��֖k���j����^�̋��Q�i�����u�ԁj�����암�Ɉʒu���Ă���B���̂��߁A2025�N�͗�O�I�ɐ�ɏ��^�̋��Q�����l����A���̌�ɑ�^�̋��Q�����l�����\��������B
�P�`�Q���̈ɓ������C��ł͍��������݊��𗬂�A�Q����{�܂ł͖k���C��ł�20�����鐅�����\������Ă���B�������A�Q�����{�`���{�͖k���C���18���̓��������߂Â��Ƃ݂��A�}�T�o�͂��̕t�߂֏W�Q����ƍl������B�܂��A�R���ȍ~���������H��A�^��Ő��ڂ��A�����͂�⍂�߁`�ɂ߂č��߂Ő��ڂ���Ɨ\������Ă���i�ߘa�U�N�x��Q���m���킵�ށA�}�A�W�A���Ηޒ������C���\���c�j�B���̂��Ƃ���A��r�I�������Ⴂ�k���C��ŋ��ꂪ�`�����ꑱ����\���������B
�i�E�j����
�ɓ������C��ŋ��l�����}�T�o�́A�R���i������27�`30cm�j����̂ƂȂ�A�S�Έȏ�i31�`35cm�j��������Ɨ\�������B���̗\���́A12�����_�̎務��ł����֖k���̋��Q����̂Ƃ��A12��23���ɏ����u�ԂŐ��g�����ꂽ�쉺�Q�Ǝv���鐬���̋��Q����������\�����l�����ē��������̂ł���B
12���P���ɏ�֖k���ő��Ƃ��ꂽ�k���܂��Ԃ̋��l�ł́A27�`30cm�̂Q���i�����R���j����̂ł������B����A12��23���̏����u�ԂŐ��g�����ꂽ�}�T�o��31�`35cm����̂ł���A���q���`�œ���ꂽ�}�T�o�̔N��茋�ʂƂ̔�r����A�R���i�����S���j�����S�Ɛ��肳���B�Ȃ��A�����u�ԂŊm�F���ꂽ�悤�ȓ쉺�Q�Ǝv���鐬���̋��Q�́A�����_�łقƂ�NJm�F����Ă��Ȃ����Ƃ���A��̂͏�֖k���̏��^�̋��Q�ɂȂ�ƍl������B
|
|
����ʃg�b�v�ɂ��ǂ�
�R�D�S�}�T�o�̋���
�i1�j�\���i2025�N1�`6���j
�@�i�A�j���V�ʂƋ��l��
�@�i�C�j�����E����
�@�i�E�j����
�i2�j����
�i�A�j���V�ʂƎ�����
2025�N�P�`�U���̖_���CPUE��2024�N�P�`�U��������ƍl������B�������A2023�N����͖_��ԑ��Ƃ��������������Ă���A�V�`11���̗��V�ʂf�ł��Ă��Ȃ��ƍl������B�܂��A2024�N�V�`11���̖_��ԁE�������������̋����o�߂��F�����Ȃ��������߁A�O�N���`�����ƍl������B
�i�C�j���������
2025�N�P���ȍ~��������֍s���p�����邱�Ƃɉ����A���������̌����Ȗk���p�����Ă��邱�Ƃ���\�������B�B
�i�E�j����
2023�A2024�N�͖k���C��ł���哇��g�◘���ł̑��Ƃ��قƂ�ǂ��߂Ă���B���ĎO����ӊC��ŋ��l����Ă����̂����傫�����߁A���߂Q�N�̂P�`�U���̋��l���̔������g�����画�f�����B�܂��A�N��Ɋւ��Ă͍ŋ߂T�N��Age-Length-Key�̕��ς��画�f�����B
|
|
�Ȃ��A����p�ɂ́A�u������v�������p���������iPDF�t�@�C���j�B
�ڍהłɂ��ẮA�u������v���������������iPDF�t�@�C���j�B
����ʃg�b�v�ɂ��ǂ�
|
![]() �@�ҍ����u�ӂ��イ�v�@
�@�ҍ����u�ӂ��イ�v�@![]() �@�C���A���������̏��F��s�O���T�o���C���������@
�@�C���A���������̏��F��s�O���T�o���C���������@![]() �@�ߘa6�N1���`6���̌������C���\��
�@�ߘa6�N1���`6���̌������C���\��![]()