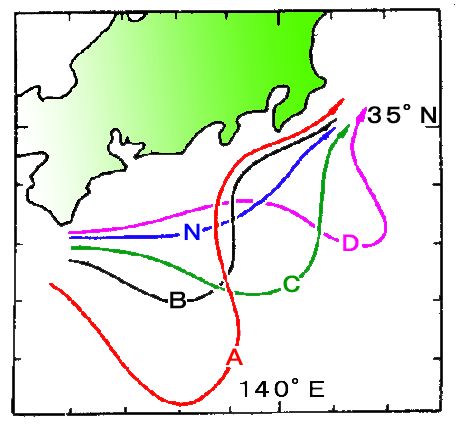海況、資源動向の情報:一都三県サバ漁海況検討会等
 待合室「ふきゅう」
待合室「ふきゅう」  海況、資源動向の情報:一都三県サバ漁海況検討会
海況、資源動向の情報:一都三県サバ漁海況検討会  令和5年1月〜6月の県内漁海況予測
令和5年1月〜6月の県内漁海況予測
|
令和5年漁期サバたもすくい網漁、棒受網漁の見込み(令和5年1〜6月)
令和5年01月11日:静岡県水産・海洋技術研究所
1.海況
(1)黒潮(2023年1〜6月)
(2)説明
1月10日現在、黒潮は、御前埼に接近した後東進し、銭洲〜御蔵島付近を通過した後、房総沖で離岸し、北東に流れている。水温は、伊豆諸島北部19.5〜20.5℃、三宅島20〜20.5℃、銭洲海域20.5〜21℃であった。
黒潮は期間を通じてA型で推移し、伊豆諸島海域の西側を北上する。その後、御前埼沖で向きを東に変え、銭洲周辺や三宅島周辺を通過しやすい。このため、これらの海域では漁場水温が上昇する。また、北部海域へも黒潮からの暖水が波及しやすく、波及時には漁場水温が上昇する。一方、房総沖では低気圧性渦の接近により一時的に離岸するものの、概ね接岸傾向で推移し、黒潮から暖水が波及しやすい。
|
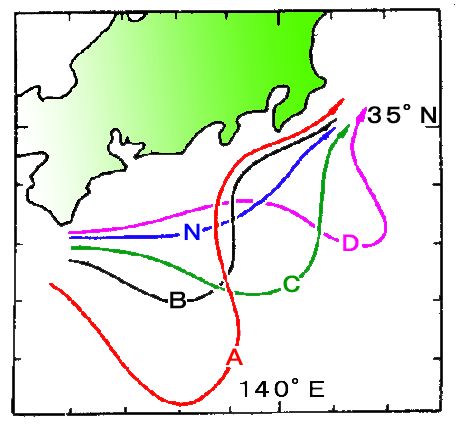 |
▲画面トップにもどる
2.マサバの漁況
(1)予測(2023年1〜6月)
(ア)来遊量と漁獲量
(イ)漁期・漁場
(ウ)魚体
(2)説明
(ア)来遊量と漁獲量
(イ)漁期、漁場
(ウ)魚体
|
 |
▲画面トップにもどる
3.ゴマサバの漁況
(1)予測(2023年1〜6月)
(ア)来遊量と漁獲量
(イ)漁期・漁場
(ウ)魚体
(2)説明
|
(ア)来遊量と漁獲量
全年級群を合わせた来遊量の予測には、年別の1〜6月と前年7〜11月の棒受網CPUE(操業隻数あたりの漁獲量)の相関関係(図1)を使用した。今回の予測期間(2023年1〜6月)における来遊量は、前年7〜11月の棒受網CPUEの値から前年同期の88%と推定され、来遊量は前年をやや下回ると考えられた。これまでの1〜3歳魚の年級群別の来遊量予測には、小川港所属のさば棒受網船の標本船日報から求めた海区ごとの1揚網あたりの漁獲量と年齢別漁獲重量から算出した各年級群の年別の前年7〜11月の資源密度指数の累積値(以下、累積資源密度指数)と、1〜6月の累積資源密度指数との相関関係から予測していた。しかし、近年の資源量低下に伴い予測値と実際の値が合わない可能性があった。そこで資源状態を表す指標として、令和3年度ゴマサバ太平洋系群資源評価において示された親魚量(SB)と、MSYを実現する水準となる親魚量(SBmsy)の比(以下、SB/SBmsy)を用い、SB/SBmsyが1以上と1未満の年に分けて分析した。その結果、SB/SBmsy<1の年の年級群の場合、明け1歳魚、2歳魚及び3歳魚において、前年の7〜11月の累積資源密度指数と1〜6月の累積資源密度指数の間に相関関係が見られた(図2)。令和3年度ゴマサバ太平洋系群資源評価によると、2015年以降、資源全体のSB/SBmsyは1未満であるため、今回の来遊予測ではSB/SBmsy<1の年の年級群における資源密度指数を用いた。
1歳魚(2022年級群)について、2023年1〜6月の累積資源密度指数は前年の487%と推定されたが(図2)、7〜11月の棒受網による漁獲割合は3.9%であった。そのため、来遊量は前年を上回ると考えられるが、予測期間における漁獲の主体とはならないと考えられる。
2歳魚(2021年級群)について、累積資源密度指数は前年の411%と推定されるが(図2)、2022年7〜11月の棒受網による漁獲割合は19.3%であった。そのため、来遊量は前年を上回ると考えられるが、予測期間における漁獲の主体とはならないと考えられる。
3歳魚(2020年級群)について、累積資源密度指数は前年の676%と推定され(図2)、2022年7〜11月の棒受網による漁獲割合は48.7%であった。そのため、来遊量は前年を上回り、予測期間における漁獲の主体となると考えられる。
4歳(2018年級群)以上について、昨年まで行ってきた予測では4歳以上の残存資源は多くないとしていたが、2021年及び2022年の1〜6月の漁獲割合はそれぞれ43.7%、64.6%と漁獲の主体であった。当該期間に漁獲される4歳以上の多くは三陸海域から南下回遊してくる産卵親魚と思われるため、現時点でその来遊量を推定するのは困難であるが、直近2年の傾向から今漁期においても主体となると考えられる。水産研究・教育機構水産資源研究所が試算したゴマサバ太平洋系群における2023年1月時点での4歳以上の資源量は、前年より減少傾向にあることから、来遊量は前年を下回ると考えられる。
(イ)漁期・漁場
(ウ)魚体
|
 |
なお、印刷用には、「こちら」をご利用ください(PDFファイル)。
詳細版については、「こちら」をご覧ください(PDFファイル)。
▲画面トップにもどる
|
![]() 待合室「ふきゅう」
待合室「ふきゅう」 ![]() 海況、資源動向の情報:一都三県サバ漁海況検討会
海況、資源動向の情報:一都三県サバ漁海況検討会 ![]() 令和5年1月〜6月の県内漁海況予測
令和5年1月〜6月の県内漁海況予測![]()