目 次
研究リポート① 深層水の保存にともなう成分等の変化について
イベント紹介 第7回全国青年・女性漁業者交流大会が開催される
榛南地区のサガラメ、カジメ群落の復活を目指して-藻食性魚類アイゴ捕獲に取り組んで- 坂井平田漁業協同組合青壮年部
郷土料理「がわ」を通した地域交流
御前崎漁業協同組合婦人部
深層水の保存にともなう成分等の変化について
はじめに
深層水は海洋の水深200~300m以深の海水で、低温安定、清浄、高栄養等の特性を持ち、クリーンで再生循環する21世紀型資源として水産、食品、医療、農業、エネルギー等多方面での利用効果が期待されています。静岡県も駿河湾深層水の取水施設を建設し、平成13年度から民間への給水を開始したところ、企業だけでなく一般市民の方々も多数利用されています。利用者の深層水に関する質問で多いのは使用方法に関するものですが、持ち帰った後の保存方法に関する質問も少なくありません。深層水は清浄ですが表層水の1/10~1/100の細菌(10~100個/ml)が存在します。また、保存に際して容器や空気中からの細菌の混入もありますので、保存方法によっては細菌が増える可能性があります。一方、保存方法によっては容器への吸着や分解のため成分が変化する可能性もあります。そこで、深層水や脱塩水、濃縮水の保存方法について検討しました。
材料及び方法
1 深層水(原水)保存試験
駿河湾深層水取水施設で採水した687m深層水(以下原水)を市販の20Lポリエチレンタンク3本に採水し1本を冷蔵庫(冷暗所区、4~8℃)、1本を20℃インキュベーター(常温明所区、庫内灯点灯)、1本をアルミ箔で遮光し20℃インキュベーター(常温暗所区)に収容し30日間保存しました。この間定期的に栄養塩類(アンモニア、亜硝酸、硝酸、リン酸、珪酸)と主要成分(Cl‐,SO42‐,Na+,K+,Ca2+,Mg2+)及びクロロフィルa濃度を測定しました。また、100ml滅菌ポリエチレンビン30本に採水し、各10本を上記の冷暗所、常温明所及び常温暗所に保存し、定期的に取り出して細菌数を計数しました。生菌数計数は海洋細菌用培地を用い、海水由来の細菌類を計数しました。
2 脱塩水保存試験
逆浸透膜を用い原水を脱塩水と濃縮水に分離し、脱塩水は原水同様に20Lポリエチレンタンクと100ml滅菌ポリエチレンビンに取り分け冷暗所、常温明所、常温暗所に30日間保存し、主要成分(Cl‐,SO42‐,Na+,K+,Ca2+,Mg2+)及び生菌数、クロロフィルa濃度を経時的に測定しました。生菌数計数用培地は食品等の検査に用いる一般細菌用培地を使用しました。
3 濃縮水保存試験
逆浸透膜で分離した濃縮水も原水同様に20Lポリエチレンタンクと100ml滅菌ポリエチレンビンに取り分け冷暗所、常温明所、常温暗所に保存し、主要成分、生菌数及びクロロフィルa濃度を経時的に測定しました。生菌数計数は海洋細菌用培地を用い、海水由来の細菌類を対象としました。
結果及び考察
1 深層水(原水)保存試験
(1)生菌数:生菌数の経時変化を図1に示しました。
取水直後の原水中の生菌数は10~102個/mlレベルと非常に少ないですが常温では明所区、暗所区とも5日目には105個/ml、10日目には106個/mlまで急激に増加しました。しかし、冷暗所区では30日後まで採水直後と同じ10~102個/mlレベルで推移しました。
(2)栄養塩類等:pH、リン酸態リン及びクロロフィルa濃度の経時変化を図2、3、4に示しました。
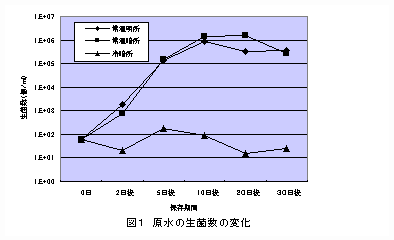 |
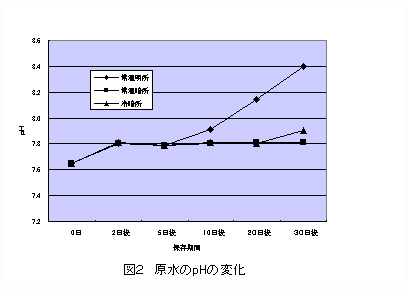 |
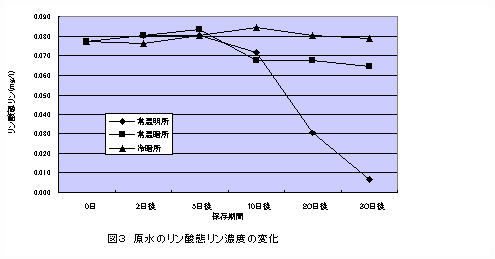 |
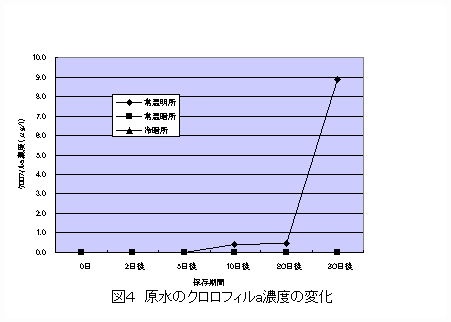 |
採水直後の原水のpHは7.7でしたが、常温明所区のpHだけが10日後から上昇し、30日後にはpH8.4になりました。しかし、他の区は総じてpH7.8付近で推移し、大きな変化はみられませんでした。
採水直後の原水のリン酸態リン濃度は0.08mg/lでしたが、常温明所区は10日後から減少し、20日後に0.03mg/l、30日後には0.01mg/lになりました。しかし、他の区は30日後も0.06~0.08mg/lの範囲でほとんど変化がありませんでした。
採水直後の原水のクロロフィルaは0.01μg/l以下でしたが、常温明所区は10日後に0.41μg/l、20日後に0.45μg/lに増加し、30日後には8.9μg/lに急増しました。しかし、他の区は30日後も0.01μg/l以下で変化がありませんでした。
このように常温明所区のみでpHの上昇、リン酸態リンの減少、クロロフィルaの増加等が生じた原因は、光を透過する容器であったことから微細藻類が増殖したものと思われます。
(3)主要成分:深層水中の主要成分であるCl‐,SO42‐,Na+,K+,Ca2+,Mg2+は30日後まで大きな変化はみられませんでした。
2 脱塩水
(1)生菌数:脱塩水中の生菌数の経時変化を図5に示しました。
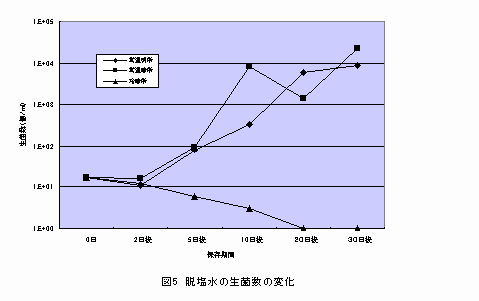
脱塩水は逆浸透膜通過の際に細菌も除去されますが、採水までの間に細菌が混入し、わずかですが検出されました。これを常温に置くと10日後に104個/ml に増殖し以後同レベルで推移しました。しかし、冷暗所では徐々に減少し、20日後には検出されなくなりました。
原水に比べて細菌の増殖量が少ないのは逆浸透膜により細菌の餌となる有機物が除去されたためと推察されます。
(2)クロロフィルa濃度:各区ともクロロフィルa0.01μg/l以下で30日後まで変化はありませんでした。
(3)主要成分:Cl‐,SO42‐,Na+,K+,Ca2+,Mg2+は30日後まで大きな変化はみられませんでした。
3 濃縮水
(1)生菌数:生菌数の経時変化を図6に示しました。
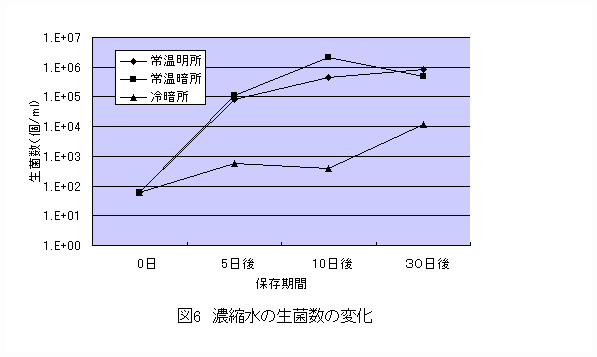
濃縮水の製造直後の生菌数は原水と同レベルでしたが、常温明所区、暗所区とも5日目には105個/ml、10日目には106個/mlまで急激に増加しました。しかし、冷暗所区では5日後に103個/ml、20日後には104個/mlレベルとなりましたが、その後は同レベルで推移しました。
(2)クロロフィルa:濃縮水のクロロフィルa濃度は30日後まで0.01μg/l以下で推移しました。
まとめ
深層水は清浄で細菌数も非常に低レベルで、それから製造した脱塩水、濃縮水も同様です。しかし、室温に放置すると細菌類が急速に増殖します。今回の試験では滅菌容器を用い他からの細菌の混入を防ぎましたが、通常は保存する容器や大気中からの細菌の混入もありますので増殖速度はさらに速まり、常温に放置した場合数日で細菌数は106個/ml以上になるものと思われます。
また、ペットボトルやポリエチレンタンク等の透明、半透明の容器は常温に放置すると微細藻類が増殖し成分が変化する可能性があります。
駿河湾深層水の利用案内にも保存は「10℃以下で保存し10日程度」とあります。深層水は清浄でも保存方法により細菌類や成分が変化しますので、冷蔵庫等の冷暗所に保存し早めに使用するようお願いします。
(深層水プロジェクトスタッフ 五十嵐保正)
ア・ラ・カルト 標識
標識放流は調査としては一般的ですが、その目的は、生物の移動範囲を捉えたり、生き残る確率を調べたり、生態調査であったり、あるいはいくつもの重複した目的があったり様々です。また、使われる標識の種類も、調査の目的や、生物の大きさなどによって決められていきます。
ここでは、異なったタイプの標識とこれを用いた最近の事例を紹介します。標識放流された生物が再び獲られる確率を再捕率と呼びますが、再捕率は決して高いものではありません。もし、標識の付いた魚やカニなどを見つけた場合は、必ず水産試験場までお知らせくださるようお願いします。
スパゲッティ型標識
スパゲッティ型標識(第1図)は5~7㎝程度の小型の魚類にも装着できる利点がありますが、魚体が傷つくために、外傷がもとで死亡したり、標識が抜け落ちたりすることがあります。また、標識が小さいため、魚体が大きくなった時に、埋没して、外部から見えなくなることもあります。
最近、スパゲッティ型標識を用いたクエの標識放流が実施されました。クエは外洋に面した岩礁海域に生息するハタ科の「高級」魚です。県温水利用研究センターでは、クエの人工種苗生産に着手し、平成13年10月に御前崎町地先に平均体長22cmのクエ515尾にピンクのスパゲッティ型標識を装着し、放流しました(第2図)。クエの標識放流は静岡県では初めてですが、九州で実施された例では、岩礁等に放流するとほとんど移動しないことが知られています。今回の放流では、5か月後まで放流海域で漁獲された例がありますが、7か月経過した時期に三重県で再捕され、クエの広範囲な移動事例が初めて示される結果となりました(第3図)。どちらかといえば、クエは滞留性が非常に高い魚であり、御前崎近海での再捕も今後あるのではないかと期待しています。
背骨ディスク型標識
背骨ディスク型標識(第4図)は通常、大型の魚類等に用いられる標識で、脱落などの心配がない標識です。装着に少し時間がかかるので、その間おとなしくしている魚等に有効です。この標識については、タカアシガニの事例(第5図)があります。第6図に示す結果は、平成12年5月に戸田村商工会等が行った放流に、ディスク背骨型標識を付けた結果です。73個体のタカアシガニを放流したところ、2か年間で8個体の再捕の報告がありました。三重県の熊野灘まで移動した例が2例あり、駿河湾のタカアシガニ資源が熊野灘まで繋がっていることが分かります。標識が甲羅についているため、タカアシガニが脱皮をすると、標識ははずれてしまい、長期間の採捕は望めませんが、確実な標識といえるでしょう。
アーカイバルタグ
これは、近年の電子技術によって開発されたデータ記録型標識です(第7図)。放流前に魚類の腹腔内に10cmの記録機を手術で埋め込み、縫合の後、放流します(第8図)。再捕された魚から標識を取り出し、記録されたデータをパソコンで読み出します。この標識は重量が50gあり、魚にとって、手術と共に負担になる欠点があります。
トラフグでアーカイバルタグを用いた調査が進められています。従来の標識とは異なった情報が収集されます。平成11年3月に6尾、さらに、平成14年5月19日に5尾のアーカイバルタグの放流を行いました。再捕されたデータを解析した結果(第9図)では、標識魚が一定の水深にとどまり、日中でも照度が0(ゼロ)を記録している状態が観察され、トラフグが砂潜行動を取っているものと推察されました。今年5月に放流したトラフグは今秋以降再捕されると思われます。
標識に代わる形態特徴
厳密には標識とはいいがたいのですが、人工生産した種苗にはいくつか天然にない特徴を持っている場合があります。トラフグの場合、近年、人工種苗には『口ひげ』に似た紋様があるのではないかといわれています(第10図)。他の標識と異なって魚にストレスも傷も与えなくてもついているという優れた特徴を持っています。昨年度この模様に気がついたのは、(社)日本栽培漁業協会の種苗生産の担当者ですが、現在、人工種苗であれば必ず口ひげの紋様があるのか、天然魚は口ひげの紋様がないのか、現在調査を進めているところです。アーカイバルタグのように細かな情報は得られませんが、市場に上がってくる魚の中に、種苗放流されたのトラフグがどの程度混じっているのかなど、目的によっては優れた標識になり得ます。
(漁業開発部 安井港)
第7回全国青年・女性漁業者交流大会が開催される
3月6~7日に東京都港区虎ノ門パストラルで全漁連が主催する第7回全国青年・女性漁業者交流大会が開催されました。本県からは、坂井平田漁協青壮年部と御前崎漁協婦人部が日頃の成果を発表しました。その結果、坂井平田漁協青壮年部は水産庁長官賞を、また御前崎漁協婦人部は全漁連会長賞を各々受賞しました。
以下に、発表要旨を特に活動内容に焦点をあてて紹介します。
榛南地区のサガラメ、カジメ群落の復活を目指して-藻食性魚類アイゴ捕獲に取り組んで-
坂井平田漁業協同組合青壮年部
研究グループの組織と運営
私たち坂井平田漁協青壮年部は昭和37年に結成され、現在の部員は13名で、サガラメ、カジメ等の復活に向けた取組みや、榛南地域栽培漁業推進協議会を中心とした栽培漁業への取組みに積極的に参加しているほか、先進地の漁業視察勉強会などを行っている。
研究、実践活動課題選定の動機
榛南地区における採藻漁業の歴史は古く、当地区相良町の名前が由来となったサガラメ漁は平安時代から行われ、冬場の重要な収入源として全組合員の約8割が従事する主要漁業であった。しかし、昭和60年頃から海藻が枯れ、藻場がなくなる「磯焼け」が発生し始め、まず地頭方でサガラメの漁獲量が減少しはじめ、平成3年頃からは坂井平田でもサガラメの漁獲量が減少しはじめた。現在では、当地区の海藻群落のほとんどが消滅してしまっている。磯焼けの進行に伴い、これらの海藻類を餌とするアワビも激減し、磯焼け発生以前は20トン近かった漁獲量は5トン以下にまで落ち込んだ。
このような状況の中、サガラメ、カジメ群落の保存と復活を目指して「榛南地域磯焼け対策推進協議会」平成8年に発足したが、私たち青壮年部では協議会発足以前から、サガラメの養殖試験を行うなど階層群落復活への取組みを積極的に行ってきた。
サガラメ養殖を行う際、早春にサガラメを沖に出して養成すると、数ヶ月は順調に成長するものの、毎年夏になるとちぎれたり、短くなった葉が目立ち始め、9月頃には茎だけになったり、枯れてしまうという状況が何年も続いた。その後の水産試験場の調査の結果、夏以降葉が短くなったり、茎だけになるのは草食性の魚アイゴによる食害が原因であり、この食害を防がなければ海藻群落の復活は望めないことなどがわかった。
アイゴはその独特の磯臭さから、本県では「ねしょんべん」「猫またぎ」と呼ばれ、ごく一部の地域を除いて食習慣はなく、商品価値は極めて低い。また、ひれに毒があるため榛南地区では網にかかってもそのまま海に捨てるような魚で、漁獲による数の減少はほとんど望めない。そこで青壮年部では、海藻群落復活のために刺網や定置網によるアイゴの捕獲に取り組むことにした。
研究、実践活動状況及び効果
1 刺網での捕獲
平成12年は青壮年部員が中心となり、カジメの移植を行っている海域周辺に当番制で刺網を仕掛けてアイゴを捕獲した。平成13年は青壮年部員以外のエビ網、刺網漁業者にも協力を依頼し、対象海域を移植海域周辺から榛南地区全体に拡大して、捕獲の効率化を図った。
2 定置網での捕獲
榛南地区には定置網が4か統あり、例年5月下旬頃からアイゴが網に入る。これまではアイゴは商品価値がないうえ、ひれに毒があって取り扱いが難しいので、そのまま海に戻していたが,陸に揚げることにした。
3 アイゴ捕獲の成果
平成12年は刺網では、7~11月に約160kgのアイゴを捕獲し、定置網では、6~8月を中心に4トン弱を捕獲した。平成13年度は、青壮年部以外の漁業者の協力もあって、刺網では前年の約10倍にあたる1.5トン、定置網では約3トンを捕獲した。アイゴ1尾を300g程度とすると、平成12,13年の2年間で約9トン、30,000尾のアイゴを捕獲したことになる。
4 アイゴ捕獲後の養殖サガラメの変化
平成7年からの試験開始以来、一度も秋を越すことができなかった養殖サガラメだが、平成13年は、深いところのサガラメを中心に食害を受けなかった個体が多く、食害を受けた個体からも新しい芽が出てきていることが確認され、収穫及び出荷が確実視されるまでになった。
5 アイゴ捕獲後のカジメ群落の変化
捕獲を行う以前は、カジメの母藻投入や移植によってカジメ群落ができても、食害が最も強くなる夏~秋を越せず、11月頃には群落は消滅していた。ところが、捕獲後の平成12年は、食害により葉が短くなっているカジメもあったが、小さいカジメ群落を1年間維持することができた。さらに、維持した群落のカジメから胞子が落ち、そこから新しいカジメが生えていることも確認された。平成13年は、夏場の台風の影響でカジメの本数は前年より少なくなるという被害はあったが、葉はたくさん残っており、食害が前年より明らかに少ないことが確認された。また、場所によっては磯焼け以前の榛南の海を思わせる立派なカジメも多数確認できるなど、群落は前年以上の良い状態のまま冬を迎えることができた。
波及効果
今回青壮年部を中心にアイゴを積極的に捕獲するとともに、磯焼けについて漁師仲間で話をしていくうちに、榛南地区の漁業者全体が,磯焼けや自分達の生活の場である海の環境について関心を持つようになった。また、海藻群落回復のための手段としてアイゴなどの藻食性魚類の捕獲が有効であることが確認できた。
今後の課題
1番の課題は捕獲したアイゴの処理方法である。平成13年には、食習慣のある沖縄県へ定置網で水揚げされたアイゴの一部を試験的に出荷してみたが、コストの問題もありうまくいかなかった。一方、アイゴを刺身,フライ,干物などに加工して簡単な食味試験を行ったところ、アイゴ独特のくさみにより不評なものもあったが、フライ、みりん干しなどでは思った以上の高評価が得られた。
今後は「アイゴ=くさくて食べられない」という先入観を払拭し、地元での食用としての消費をはかり、アイゴの商品価値を高めることでアイゴ捕獲の効率を高め、さらには未利用資源の有効活用にもつなげていきたい。そして、多くの人の努力によって我々の念願である榛南地区のサガラメ、カジメ群落が復活し、アワビやサザエが再び戻ってきたら、その海藻群落をいつまでも維持していけるように海の環境保全などにも気を配り、豊かな海を自分達の後輩や次の世代に残していきたい。
御前崎漁業協同組合婦人部
実践活動課題選定の動機
御前崎町には昔のカツオ漁の漁師が船上でとれたてのカツオを使って作った「がわ」という郷土料理が伝わりますが、最近では地域の人達のなかにも「がわ」を知らない人が多くなってきました。
そこで、婦人部が恒例で行っている老人ホームの慰問や子供達との交流会のおりに「がわ」を食べてもらい郷土料理を伝えていくとともに地域交流を図ろうと考えました。さらに、マスコミを利用した「がわ」のPRを行い、町を訪れる若い人達や都会の人達にも「がわ」の味を知ってもらおうと考えました。
実践活動状況及び成果
1 郷土料理「がわ」
「がわ」は御前崎に伝わる郷土料理で、昔、小早船と呼ばれるカツオ船の漁師が、カツオを一杯釣って汗を流した後で食べる唯一の労働食であったといわれています。作り方は簡単で、新鮮なカツオのタタキに水と氷と味噌を入れてかき混ぜて、これに薬味を入れて出来上がりです(第2表、写真)。薬味には玉葱、胡瓜、葱、生姜、大葉、梅干しなどを使います。何より大切なのは、新鮮なカツオを使うことです。「がわ」の名前の由来ですが、なべの中でかき混ぜる時にガワ、ガワと音がするからだと言われています。
2 老人ホームの慰問
毎年4月下旬には、町にあります老人ホーム「灯光園」に慰問に行きます。灯光園は静かで空気のよい環境に恵まれた所にあります。 私達婦人部は、灯光園が設立された最初の年から初がつをを持って慰問に行くようになり、もう25年になります。今年は役員23名で、全部で14本30㎏程のカツオを調理しました。カツオは頭を取り、三枚におろして、お刺身、煮物、たたき、そして小さく切って酢漬けもつくりました。最後に御前崎の郷土料理「がわ」を作りました。毎年、皆さんが私達のカツオを楽しみにしていただいているとのことで、私達もそれを励みに、また楽しみにしています。
3 「がわ」料理のテレビ取材
6月下旬、地元のテレビ局から港で「がわ」料理を作ってほしいと電話がありまして、驚きました。町の宣伝にもなることですし、これも私達の役目だと思い、お引き受けすることにしました。
当日、朝7時30分、婦人部員10名は市場に集まり、漁協からカツオ2本いただき、「がわ」を大きななべに2つ作りました。市場で働く人やちょうど一仕事終えて入港したしらす船の漁師にも食べていただきました。「運がよかったよなあ」と言って喜ばれ、「おいしいおいしい」と言って食べていただきました。
後日、この様子が1分半ほどでしたが『カメラマンが見た御前崎のみなと』と題して放送されました。活気あふれる映像で、カツオのセリの様子、おろす所、「がわ」料理を食べる所などが、上手に構成されていました。手伝ってくれた皆さんもきれいに映り、まずは安心、これで少しは宣伝にもなるかなと思いました。
4 小学生との交流会
9月29日には榛南地区4漁協の婦人部員と地元の小学生との交流会が行われました。毎年秋に小学校の課外授業の一環として行われるもので、今年は5年生60名、先生、婦人部員などで総勢90名になりました。交流会は御前崎港内で子供達の釣り大会の後、駐車場にテントをはり昼食会をしました。いか、あじを焼き、カツオの「がわ」を作りました。皆さんおいしいと言って食べてくれ、子供たちとのふれあいは、楽しいひとときでした。後日、子供たちからたくさんのお礼の手紙がきました。
波及効果
地元で獲れる新鮮なカツオを使ってできる郷土料理「がわ」を通して、地域のお年寄りや子供たちとの交流ができました。特に老人ホームのお年寄り達は、毎年私達のカツオ料理を楽しみにしていただいているそうです。また、子供達との交流では、漁師以外の家庭の子供にも郷土の味を知ってもらえたのではと思っています。
「がわ」料理のテレビ放送では、放送後すぐに「がわ」についての問い合わせがあったり、魚屋さんに「がわ」を作るからといってカツオを買いにきたお客さんがあったそうです。テレビの力はすごいと思いました。最近は地元の民宿や料理屋さんでも「がわ」を出すところが増えてきました。
今後の課題
私達は普段、新鮮な魚がある時は何気なく『今日は「がわ」にするか』と言って気軽に食べていますが、テレビで放送されるのを見ますと郷土の料理として大切な食文化なんだと改めて思い、「がわ」料理を広め、後の人達にも伝えていくことは私達の大切な役目だと思いました。地元の新鮮な魚を使った郷土料理を通じて、地域の人たちとの交流が図れるならこんなに素晴らしいことはありません。これからは地元の人だけでなく、最近、多くなった若いウインドサーファーや観光客にもぜひこの味を紹介しようと皆さんと力を合せて一生懸命頑張りたいと思います。
4月6日に爪木崎北東沖5.4km、水深245mの海域にマリンロボ4号機が設置されました。 ブイの情報は下記のとおり従来と同じ番号ですが、ガイダンスにそって番号を入力すると、ほしい情報を選択して入手できますので、どうぞご利用ください。
|
|
|
調査内容 |
期間 |
|
富士丸 |
ビンナガ・カツオ調査 |
4月9日~4月26日 |
|
東沖ビンナガ調査 |
5月8日~6月10日 |
|
|
東沖ビンナガ調査 |
6月24日~ |
|
|
駿河丸 |
鯖標識放流調査 |
4月3日~4月4日 |
|
地先定点観測 |
4月8日~4月11日 |
|
|
水質調査(奥駿河湾) |
4月16日~4月16日 |
|
|
サバ標識放流調査 |
4月23日~4月24日 |
|
|
サバ標識放流調査 |
5月1日~5月2日 |
|
|
地先定点観測 |
5月7日~ 5月9日 |
|
|
深層水調査(駿河湾) |
5月14日~5月15日 |
|
|
サバ標識放流調査 |
5月20日~5月21日 |
|
|
サバ標識放流調査 |
5月22日~5月23日 |
|
|
深層水調査(駿河湾) |
5月28日~5月29日 |
|
|
サバ標識放流調査 |
5月30日~5月31日 |
|
|
地先定点観測 |
6月3日~6月5日 |
|
|
マリンロボ調査 |
6月10日~6月11日 |
|
|
サバ標識放流調査 |
6月13日~6月14日 |
|
|
サクラエビ産卵調査 |
6月17日~6月18日 |
|
|
マリンロボ調査 |
6月19日~6月20日 |
|
|
水質調査(奥駿河湾) |
6月24日~6月24日 |
|
|
サクラエビ調査 |
6月25日~6月26日 |
|
|
サバ標識放流調査 |
6月27日~6月28日 |
|
月日 |
事 柄 |
|
4.1 |
事例交付 |
|
5 |
富士丸・駿河丸安全祈願祭 |
|
8 |
焼津水産高校入学式 |
|
10 |
漁業高等学園入学式 |
|
16 |
浜岡原子力発電所前面海域調査委員会(浜岡町) |
|
25 |
普及推進会議 |
|
5.10 |
水産事業概要説明会(静岡市) |
|
16 |
実習船やいづ壮行式 |
|
21 |
水産加工連総会(静岡市) |
|
27 |
焼津水産加工センター竣工記念式典(焼津市) |
|
6.3 |
焼津市海洋深層水利用研究会(焼津市) |
|
6.4 |
環境放射能測定技術会(静岡市) |
|
5 |
沼津あじ寿司選考委員会(沼津市) |
|
14 |
静清・西遠流域下水道河川海洋調査専門家会議(浜松市) |
|
19 |
静岡県食品産業協議会通常総会(静岡市) |
|
20~21 |
東海ブロック水産試験場長会(茨城県) |
|
28 |
水産加工技術セミナー |